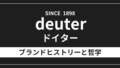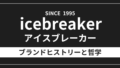2004年、神戸の一軒家から始まった小さなアウトドアブランド「ファイントラック」。
創業者の金山洋太郎氏が山岳少年時代から培った情熱と、30年間の繊維業界経験が融合して生まれたこのブランドは、今や世界中のアウトドア愛好家から絶大な支持を受けています。
世界初の撥水アンダーウェア「ドライレイヤー」や革新的な保温素材「ファインポリゴン」など、業界の常識を覆す技術革新の背景には、「遊び手が創り手」という独特な哲学がありました。
創業から20年、数々の困難を乗り越えながら歩んできたファイントラックの奇跡の物語をお伝えします。
遊び手が創り手として歩んできたファイントラックの創業物語
ファイントラックの物語は、一人の山好きな少年から始まります。現在のファイントラック代表取締役である金山洋太郎氏の歩みは、まさに「遊び手が創り手」という哲学を体現したものです。
山への純粋な愛情から繊維のプロフェッショナルへと成長し、運命的な出会いを経て、ついには独立起業に至る道のりを見ていきましょう。
山岳少年が繊維のプロフェッショナルになるまでの軌跡
金山洋太郎氏の山への愛は、幼少期から始まっていました。六甲山の麓で育った少年時代、学校が終わってもそのまま山の中で遊び、帰りが夜の9時や10時になるほど山に夢中でした。登山との本格的な出会いは小学生の時で、父親に芦屋のロックガーデンに連れて行ってもらったのがきっかけです。
高校では山岳部に入部しましたが、当時は高校生のクライミングが禁止されていたため、卒業と同時に社会人の山岳会に参加。この頃から本格的なクライミングやバックカントリースキー、MTB、カヤック、釣りといった多様なアウトドア活動に没頭するようになります。
そんな金山氏の人生を大きく変えたのが、登山を通じて知り合った人からの声かけでした。金山氏が既成の道具を自分で改造している姿を見て「ものづくりができるのでは」と声をかけられ、ダンロップの関連会社に入社することになったのです。
川での偶然の出会いが運命を変えた瞬間
ファイントラック誕生のきっかけとなったのは、川での偶然の出会いでした。多彩なアウトドアスポーツ経験を持つ金山洋太郎氏と、スキーカヤックのエキスパートである橋本剛氏が、ある川で頻繁に出会うようになったのです。
四季を通じてアウトドアを楽しむ二人は自然と意気投合し、一緒に冒険に出かけるようになりました。当時、二人はそれぞれ異なる分野で活躍していました。
この出会いが後にファイントラックの強みとなるシナジー効果を生み出します。金山氏の豊富な繊維の知識とコネクション、そして橋本氏の外資系企業で培った緻密な戦略マーケティング。この二つの専門性が組み合わさることで、本気で遊ぶ上級者ほど真価を実感できる製品が生まれる土台ができあがったのです。
大手メーカーでの葛藤が生んだ独立への強い意志
ダンロップの関連会社で30年間働く中で、金山氏は「繊維のプロ」と呼べるまでに成長しました。同社の前身は糸商で、繊維の知識やノウハウが豊富にあり、そこで金山氏は徹底的に鍛え上げられたのです。
しかし、会社の成長とともに方針が変わっていきます。当初はハイレベルな登山者など、コアユーザー向けの製品開発に携わっていましたが、会社が大きくなるにつれて「大衆向けにコストダウンして普及品を創る」方針へと転換していったのです。
この変化に金山氏は大きなジレンマを感じるようになります。
一方、橋本氏も「アウトドア業界で仕事がしたい」と考えていました。そんな二人が出した答えが、「自分が働きたい会社を自分たちで作る」ということだったのです。こうして、2年間の構想期間を経て、2004年にファイントラックが誕生することになります。
神戸の一軒家から始まったファイントラックの挑戦
2004年1月、神戸市内の一軒家でファイントラックの歴史が始まりました。アウトドアフリークたちが集まって立ち上げたこの小さな会社は、創業からわずか半年で存続の危機に直面します。
しかし、その困難を乗り越える過程で築かれた信念と人とのつながりが、現在のファイントラックの基盤となっているのです。
どこにもないまったく新しいモノを創るという決意
「どこにもないまったく新しいモノを」という強い思いを胸に、金山洋太郎氏は2年間の構想期間を経てファイントラックを立ち上げました。創業時から明確なビジョンを持っていた金山氏は、創業と同時に革新的な5つの商品シリーズを発表します。
その中でも特に注目されたのがドライレイヤーを含む製品群でした。当時はまだ認知度が低く、市内の一軒家をオフィスとし、たった1台の車でスタッフ総出で全国を営業に回る日々が続きます。
創業前からあった製品アイデアに対して、金山氏は確固たる自信を持っていました。特に以下の点で絶対的な支持を得られると確信していたのです。
この確信こそが、小さなスタートアップとして困難な道のりを歩み続ける原動力となりました。
創業半年で訪れた存続の危機と国産へのこだわり
2004年夏、創業からわずか半年で金山氏は早くもブランド存続の危機に立たされることになります。問題は製造工場の確保でした。当時のファイントラックはまだ小さく、生産量は現在とは比べ物にならない数十枚程度、モデルによってはわずか数枚という状況でした。
地方の小規模な工場はどんどん衰退し、生き残っているのは大量生産体制を取った大工場ばかり。そんな中で金山氏は全国を駆け回り、スキンメッシュの縫製を受けてくれる工場探しの日々が続きました。
と金山氏は当時を振り返ります。
それでも金山氏は「国産でないとあかんのや!」という信念を曲げることはありませんでした。この執念が後の品質と技術革新の基盤となるのです。
人情に支えられながら築いた工場との絆
最終的に生産量の少なかったスキンメッシュの生産を引き受けてくれた工場は、金山氏のものづくりに共感し、人情で引き受けてくれたようなものでした。商売として成り立たない小ロットの仕事を受けてくれたのは、金山氏の熱意と技術への真摯な姿勢に心を動かされたからです。
創業当時からの付き合いとなった関係会社や工場とは、現在も取引が続いています。これらの工場との関係は単なるビジネスパートナーではなく、共にファイントラックの理念を支える仲間として発展してきました。
その後、スキンメッシュは年を追うごとに生産量が倍増していきます。人情に支えられた小さなスタートから始まったファイントラックは、力になってくれた工場とともに活気づいて成長していったのです。
この経験が金山氏に教えたのは、以下のような価値観でした。
工場や人との関係性が現在のファイントラックの国産へのこだわりと品質の高さを支えているのです。
汗冷えの常識を覆したファイントラックのドライレイヤー革命
ファイントラックの代名詞ともいえるドライレイヤーは、アウトドア業界の常識を根本から覆した革命的な製品です。従来の「汗を吸い取る」という発想ではなく、「汗を肌から遠ざける」という全く新しいアプローチで、多くのアウトドア愛好家を救ってきました。
実は、画期的なドライレイヤーが誕生するまでには、3年間という長い開発期間と数々の技術的挑戦がありました。
濡れ冷えという根本問題に挑んだ3年間の開発秘話
ドライレイヤー開発のきっかけは、金山氏自身の実体験にありました。登山だけでなく、カヤックなどのウォータースポーツにも取り組む中で、濡れ冷えによるダメージの大きさを切実に感じていたのです。特にあるスタッフが濡れたウェアを着用して寒い思いをしたという体験が、開発の出発点となりました。
従来のアンダーウェアは汗を吸い取ることに重点を置いていましたが、金山氏は全く違う発想に至ります。「汗を吸い取るのではなく、撥水によって肌から遠ざける」という革新的なアイデアでした。
しかし、このアイデアを実現するのは容易ではありませんでした。開発には以下のような困難が立ちはだかったのです。
そこから3年間という長い試行錯誤が始まり、編み方や構成する繊維自体にまで開発の手を入れる日々が続きました。
世界初の撥水アンダーウェアが誕生した奇跡の瞬間
3年間の開発期間を経て、ついに世界初の撥水アンダーウェアが完成しました。このドライレイヤーの仕組みは画期的なものでした。生地自体が保水しにくいため、汗を上層ウェアへスムーズに移行させて肌のドライ感を持続させるのです。
従来のポリプロピレンに代表される疎水アンダーウェアでは、生地を構成する繊維表面に水分が膜を張って残るため、汗が肌に滞りやすくなっていました。しかしファイントラックの撥水技術は、この問題を根本から解決したのです。
ドライレイヤーの製造には特殊な技術が必要でした。特殊なメッシュは最新編機では製造できない希少なもので、0.4mmという極薄メッシュ生地の縫製は至難の技となります。
製造上の特徴として以下の点が挙げられます。
こうして汗でびしょ濡れになっても肌への濡れ戻りを防ぐ、世界初の撥水アンダーウェアが誕生したのです。
150洗80点という驚異的な耐久性を実現した技術力
ドライレイヤーの真価は、その驚異的な耐久性にあります。JISに基づく撥水性の耐久試験では、150回の機械洗濯後も80点の撥水性を発揮する「150洗80点」という結果を実現しました。この数値は、従来の撥水ウェアでは実現不可能なレベルの耐久性を示しています。
この耐久性を支えているのは、金山氏が30年間の繊維業界経験で培った深い知識と技術です。ナイロン繊維の特性を最大限に活かし、タフさと耐磨耗性に優れながら、ソフトな風合いと適度なクーリング性も兼ね備えた素材を完成させました。
技術的な特徴として注目すべき点があります。
現在、ドライレイヤーは全45種類まで展開され、通年使えるベーシック、暑い季節向けのクール、秋冬やウォータースポーツ向けのウォームと温度域で細分化されています。長袖タイプからタンクトップ、カップ付きブラまで、形状も幅広く展開されており、多くのアウトドア愛好家に愛用され続けているのです。
ダウンの弱点を克服したファイントラックのファインポリゴン開発物語
ドライレイヤーに続くファイントラックの革命的製品が、ファインポリゴンです。この保温素材は、ダウンの最大の弱点である「濡れ」に対する脆弱性を根本から解決しました。
5年近い開発期間を経て、保温素材の概念そのものを変える画期的な技術が誕生したのです。その開発過程には、従来の常識を覆す発想の転換と、3年間にわたる苦難の道のりがありました。
保温素材の概念を根本から変えた発想の転換
防寒着やスリーピングバッグの保温素材として、ダウンは長い間最高の素材とされてきました。軽量でありながら優れた保温性を持つダウンは、確かに素晴らしい素材です。しかし、山で使うことを考えると大きな欠点がありました。濡れると保温力が急激に下がってしまうことです。
金山氏は、ダウンがその軽量保温性の高さにもかかわらず、湿潤で過酷なフィールドコンディションにおいては「物凄く不向きな素材」であると認識していました。それまでの化繊メーカーによるダウン模倣の試みは、しばしばより重く、かさばり、効果の低い保温材しか生み出せていなかったのです。
ファイントラックは異なるアプローチを取ることにしました。ダウンの欠点を克服し、さらにその機能性を凌駕することを目指したのです。開発目標として以下の点を掲げました。
この発想の転換こそが、後のファインポリゴン誕生の礎となったのです。
ワタからシートへのブレークスルーが生まれた瞬間
開発の転機となったのは、「ワタではなくシートではどうか」というアイデアでした。薄い紙を重ねてくしゃくしゃにしてみると、いい具合にロフトが形成されます。これを復元力が高く吸水しない生地で作れば、保温素材として使えるのではないかと考えたのです。
この瞬間、開発の具体的な形が見えました。従来の中綿式保温材のように繊維を詰め込むのではなく、シート状の素材でロフトを作り出すという全く新しい発想です。これにより、中綿式保温材の問題点も同時に解決できることが分かりました。
シート状構造の利点は明確でした。
しかし、アイデアは固まったものの、それを製品として形にするのは別問題でした。適した素材が見つからず、理想的な素材に巡り会えても、今度は裁断と縫製が非常に困難という新たな課題が待ち受けていたのです。
3年間の開発地獄を乗り越えて掴んだ圧倒的な性能
アイデアを製品化するまでの道のりは困難を極めました。開発に取り掛かってみると、課題は山積みだったのです。まず適した素材が見つからない。ようやく理想的な素材に巡り会えたら、今度は裁断と縫製が非常に難しい。工場スタッフと何度も議論を戦わせ、試作と調整を重ねて、2012年、ついに生産にこぎつけることができました。
この時すでに、最初の着想からまる3年が経っていました。しかし、その苦労は報われました。完成したファインポリゴンの性能は圧倒的だったのです。
性能テストの結果は以下の通りです。
性能テストの数値は、濡れた状態でもファインポリゴンが他の保温素材を圧倒する性能を持つことを客観的に証明しています。2013年にスリーピングバッグとして初めて市場に投入され、翌2014年にはウェア製品も発表されたファインポリゴンは、保温素材の新たなスタンダードとなったのです。
遊び手が創り手だからこそ生まれるファイントラックの製品哲学
ファイントラックの製品が多くのアウトドア愛好家から絶大な支持を受ける理由は、「遊び手が創り手」という独特な企業哲学にあります。この哲学は単なるスローガンではなく、製品開発から企業文化まで、すべてに浸透している実践的な考え方です。
真剣にアウトドアを楽しむ人たちが作る製品だからこそ、エキスパート層からの信頼も厚く、流行に左右されない本質的な機能を追求し続けているのです。
エキスパート層から絶大な支持を受ける本当の理由
ファイントラックの製品は、特にエキスパート層からの支持が絶大です。その証拠として、2012年のトランスジャパンアルプスレース(日本海から太平洋まで416km走破のレース)で、参加者の実に9割の選手がファイントラックの「フラッドラッシュ・スキンメッシュシリーズ」を着用していたという驚くべき事実があります。
注目すべきは、同社がこれらの選手たちに商品提供をしたわけではないということです。エキスパートたちが自らの判断でファイントラック製品を選んだのです。この事実は、製品の実力を客観的に証明しています。
エキスパート層に支持される理由として以下の点が挙げられます。
「遊び手が創り手」という哲学により、開発者自身が製品のヘビーユーザーとなることで、本当に必要な機能が何かを深く理解しているのです。これがエキスパートの厳しい要求に応える製品を生み出す原動力となっています。
社員全員がアウトドア愛好家という理想的な開発環境
ファイントラックの強みは、社員たちのほとんどがアウトドア愛好家であることです。代表の金山洋太郎氏をはじめ、クライミングやバックカントリースキー、MTB、カヤック、釣りといった「遊び」を本気で楽しむ人たちが集まっています。
この環境が生み出す効果は絶大です。17時30分になると社員たちは遊びの相談を始め、社員有志総出で川などに遊びに行くことも日常茶飯事。これが商品のテストも兼ねているのです。長期休暇を取って海外に登山に出掛けることも可能な職場環境を整えることで、より多様な体験から製品開発に活かしているのです。
ファイントラックの開発環境の特徴は以下の通りです。
金山氏は「斬新な発想というのは自分が本気で遊び、真剣にフィールドに向かわないと生まれてこない」と信じており、この信念が会社全体の文化として根付いています。
流行を追わずに機能を追求し続ける不器用なまでの信念
ファイントラックの製品開発には、流行を度外視した不器用なまでの機能追求があります。金山氏は「我々がやってるアウトドアの捉え方は絶対間違っていない」という信念を持ち、「遊び手が創り手」「メイドインジャパンのモノ創り」といったミッションのもと、製品をつくり続けています。
流行には「ある意味不器用というか、度外視している部分もある」と金山氏自身が認めています。しかし、そういう部分も含めて共感してくれる人たちがファイントラック製品を購入し、自然と同じスタンスでアウトドアを楽しんでくれているのです。
この姿勢が生み出す価値は以下の通りです。
この不器用なまでの信念が、結果的に熱心なアウトドア愛好家との間に強固でほとんど家族的な信頼関係を築いています。彼らは、ギアが「自分たちの一員」によって作られていることを認識し、高いブランドロイヤルティを持ち続けているのです。
【まとめ】ファイントラック(finetrack)が歩んできた歴史
ファイントラックの20年間の歴史は、一人の山好きな少年が繊維のプロフェッショナルへと成長し、ついには世界のアウトドア業界に革命をもたらした物語です。
神戸の一軒家から始まった小さな挑戦は、「遊び手が創り手」という哲学のもと、ドライレイヤーやファインポリゴンといった画期的な技術を生み出しました。
創業半年で訪れた存続の危機も、国産へのこだわりと人情に支えられた工場との絆によって乗り越えてきました。
流行を追わず、真の機能性を追求し続ける不器用なまでの信念が、エキスパート層からの絶大な支持を獲得し、現在も多くのアウトドア愛好家に愛され続けています。