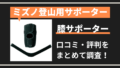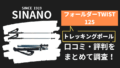登山用品店で見かける手裏剣マークのバックパック。パーゴワークス(PAAGOWORKS)というこのブランドには、2011年の東日本大震災という日本の転換点から生まれた深い物語が隠されています。
「Pack and Go!(荷物を詰めて出かけようぜ!)」という力強いメッセージを掲げ、震災後に内向きになった日本社会に向けて「外へ出よう」と呼びかけたのは、プロダクトデザイナーの斎藤徹氏。15年間のデザイナー経験で培った技術と、「人を外に連れ出す道具を作りたい」という使命感が、このブランドの原動力となりました。
「丸いけど尖っている」「三流メーカー」といった一見矛盾した言葉で自らを表現するパーゴワークス。その独特な哲学の裏には、日本人の体型に最適化された設計、ユーザーに我慢をさせない優しさ、そして初心者にも開かれた門戸という、確固たる信念があります。
今回は、震災から生まれたこの異色のアウトドアブランドの創業物語と、ものづくりに込められた想いを紐解いていきます。
パーゴワークスは震災をきっかけに「人を外へ連れ出す」使命を背負って生まれた
2011年3月11日、東日本大震災という未曾有の災害が日本を襲いました。この出来事が、一人のデザイナーの人生を大きく変え、パーゴワークスという新たなアウトドアブランドを誕生させるきっかけとなったのです。創業者・斎藤徹氏の原体験から震災後の決意まで、ブランド誕生の物語を紐解いていきましょう。
釣りキチ三平世代の少年が自転車で奥多摩を駆け巡った原体験
パーゴワークス創業者の斎藤徹氏は、1971年東京生まれ。小学生時代は「釣りキチ三平世代」として、多摩川や秋川で釣りに明け暮れていました。しかし、お小遣いは限られていたため、必要な道具は自分で作るしかありません。ルアーや浮き、毛鉤といった釣り道具を自作することで、ものづくりの楽しさに目覚めていきました。
中学生になると、興味は自転車へと移ります。片道30キロもの距離を自転車で走り、青梅や奥多摩の山々へ出かけるようになりました。そんな冒険の中でも、ものづくりの情熱は消えることはありません。
当時はまだ珍しかったフレームバッグを自作し、学校で習ったミシンの技術を使って、自分のリュックにポケットを縫い付けるなど、既製品に満足せず、自分の使い方に合わせて道具を改良し続けました。
デザイナーとして15年間抱え続けた「ものづくり」への葛藤
1998年、斎藤氏はフリーランスのバッグデザイナーとして独立します。当時、テクニカルなアウトドア用バックパックをデザインできる人材は少なく、多くの仕事に恵まれました。大手ブランドのデザインをこなしながら、ガレージブランドのように自身のオリジナル製品も製作・販売していたのです。
しかし、ここで大きな矛盾に直面することになります。デザイナーとしての彼は、常に新しいアイデアを試し、改良を重ねたくてたまらない。一方で、生産者としては、顧客のために同じ品質の製品を安定して供給する義務がある。
結果として、わずか1年半で製品が「バージョン8」にまで達してしまうような状況に陥ったことで、生産は工場に任せて自身はデザイナーに専念することを決意するのです。
東日本大震災が突きつけた「明日は当たり前に来ない」という現実
2011年3月11日の東日本大震災は、斎藤氏の人生観を根底から変えました。「明日も同じ今日があるわけではない」ことを痛感し、「もっとちゃんと生きよう」と決意します。
同時に、震災後の社会状況に強い危機感を覚えました。自粛ムードが広がり、人々がアウトドアや遊びから遠ざかっていく様子を見て、このままでは世の中が殺伐としたものになってしまうのではないかと危惧したのです。
「自分が道具を作ることで、人を外に連れ出せるかもしれない」という使命感が、彼の背中を押しました。それまで続けていたフリーランスのデザイナー業務をきっぱりとやめ、2011年に心機一転「パーゴワークス」として本格始動。震災で内向きになった日本社会に、「さあ、外へ出かけようぜ!」というメッセージを込めて、新たなブランドの歴史が始まったのです。
「Pack and Go!」というパーゴワークスの名前に込められた力強いメッセージ
パーゴワークスという独特な響きのブランド名には、震災後の日本に向けた熱いメッセージが込められています。ブランドのロゴマークである手裏剣から、「アウトドア自由主義」という哲学まで、すべてが創業者・斎藤徹氏の強い想いを体現しているのです。その一つひとつに込められた意味を探っていきます。
手裏剣マークが表現する日本の折り紙文化とものづくりの精神
パーゴワークスのロゴマークは、一目見れば忘れられない手裏剣の形をしています。このデザインの発想の原点は、実は日本の伝統文化である「折り紙」にあるのです。折り紙は、一枚の紙から立体的な形を生み出す、まさに日本のクラフトマンシップの象徴といえるでしょう。
実際、パーゴワークスの代表的な製品である「NINJA」シリーズでは、この手裏剣モチーフが製品デザインにも活かされています。特にNINJAタープは、手裏剣型という独特な形状により、30通り以上もの設営バリエーションを可能にしており、まさに折り紙のような創造性と実用性を兼ね備えた逸品となっています。
なぜ「アウトドア自由主義」を掲げるのか?
「アウトドア自由主義」というスローガンは、パーゴワークスの精神を最も端的に表す言葉です。もっと自由に道具を作り、もっと自由にアウトドアを楽しむ。この哲学の背景には、斎藤氏自身の多様なアウトドア経験があります。
彼はスノーボード、リバーカヤック、アドベンチャーレースのサポートなど、特定の分野に特化するのではなく、季節に合わせて様々なアクティビティを「そこそこ」楽しむスタイルを理想としてきました。「カテゴライズがあまり好きではない」と公言する斎藤氏は、登山、キャンプ、トレイルランニングといったジャンルの垣根を越えて、ユーザーが自分らしいスタイルで自然と向き合うことを応援したいと考えています。
この思想は製品設計にも反映されており、ハイキング用のバックパックがキャンプや自転車旅でも活躍するなど、ユーザーがアクティビティを自由に横断できるような道具作りを意図的に行っているのです。
内向きになった日本社会への挑戦状
「PAAGOWORKS」という名前は、「Let’s pack and go!」を略した造語です。日本語にすれば「さあ、荷物を詰め込んで出かけようぜ!」という意味になります。この力強いメッセージは、震災後の沈んだ空気の中で生まれました。
震災後、日本社会には自粛ムードが広がり、人々がアウトドアや遊びから遠ざかっていく様子を見た斎藤氏は、強い危機感を抱きます。「このままみんな外に出なくなったら、遊びがなくなったら世の中は殺伐としたものになってしまう」という思いから、人々を再び外へと誘う道具を作ることを決意しました。
パーゴワークスが特に「ビギナーや若い人にやさしいブランドでありたい」と強調するのも、この創業の理念に基づいています。震災をきっかけに、誰もが再び外で遊ぶきっかけを作りたい。そんなブランドの使命が、「Pack and Go!」という言葉に凝縮されているのです。
パーゴワークスが追求する「丸いけど尖っている」という絶妙なバランス
創業者の斎藤徹氏が自ら語る「丸いけど尖っている」という言葉。これはパーゴワークスの製品哲学を完璧に表現しています。
「丸い」とは初心者でも無理なく使える優しさ、「尖っている」とは他にはない革新的なアイデア。この二つの要素がどのように製品に反映されているのか、詳しく見ていきましょう。
ユーザーに我慢をさせないという徹底した優しさの哲学
斎藤氏は、一部のUL(ウルトラライト)ギアが軽量化のために快適性を犠牲にし、ユーザーにある程度の「我慢」を強いることがあると指摘しています。パーゴワークスは、その対極を目指しているのです。
身体的な負担だけでなく、精神的な負担も軽減することを重視しています。例えば、パーゴワークスが考える負担軽減には次のようなものがあります。
BUDDYシリーズの「7の字」型の大きな開口部は、荷物の出し入れを驚くほど簡単にしました。また、着脱式バックパネルは、休憩中に乾かしたり、帰宅後に洗濯したりできる実用的な機能です。ユーザーが純粋にアウトドアを楽しめることを最優先に考える、それがパーゴワークスの優しさなのです。
日本人の体型に最適化された独自の設計思想
欧米ブランドが日本市場にサイズ調整程度でローカライズするのに対し、パーゴワークスは構造設計から見直しています。日本人の体型データに基づいた独自技術の開発は、まさにブランドの強みといえるでしょう。代表的な技術革新として、以下のような特徴があります。
ユーザーからは「背負う」というより「着る」「包み込まれる」ようなフィット感だと評価されています。高重心設計により体感重量が軽減され、長時間の山行でも疲れにくい。これは、日本人の体型を知り尽くしているからこそ実現できた、「着るような背負い心地」なのです。
国内開発と海外生産のハイブリッドが生む品質とコストの両立
パーゴワークスのものづくりは、国内だけで完結しているわけではありません。デザイン開発は100%日本で行われますが、実際の生産はベトナムを中心としたアジアの提携工場が担っています。
この生産体制の特筆すべき点は、提携工場が欧米のトップアウトドアブランドの生産も手掛ける、世界水準の技術力を持つ一流工場であることです。開発プロセスの特徴として、次のような強みがあります。
小規模なメーカーであるパーゴワークスが、こうした一流工場とパートナーシップを結べていることは、高品質と優れたコストパフォーマンスを実現する生命線となっています。
なぜパーゴワークスは「三流メーカー」を自称するのか?
斎藤徹氏が好んで用いる「三流メーカー」という言葉。一見すると自虐的に聞こえるこの表現には、実は深い意味が込められています。大手ブランドでもガレージブランドでもない、独自の立ち位置を確立したパーゴワークス。その戦略的なポジショニングと、あえて「三流」を名乗る理由を探ってみましょう。
ガレージブランドでも大手でもない独自のポジション
斎藤氏は、かつては「ガレージブランド」と呼ばれることを嬉しく感じていたものの、今はもうしっくりこないと語っています。確かに、イノベーティブな精神やユーザーとの近さという点では共通するものがあります。
しかし、パーゴワークスの実態は、小規模な個人工房という一般的なガレージブランドの定義からは大きくかけ離れているのです。パーゴワークスの独自性は以下のような点に表れています。
この独特な立ち位置は、ブランドにとって極めて戦略的な「堀」となっており、他にはない価値を提供する源泉となっています。
ハードコアなULカルチャーとあえて距離を置く理由
斎藤氏は、UL(ウルトラライト)やMYOG(Make Your Own Gear)といったカルチャーが、排他的なクラブのようになってしまうことに懸念を抱いています。一部の先鋭的なブランドをリスペクトしつつも、「パーゴワークスはそういう存在ではない」と明確に線引きしているのです。
彼の信条は「誰かのためにつくる」ということ。その理由として、次のような考えを持っています。
極限まで軽量化を追求するブランドとは根本的に異なるアプローチであり、より多くの人にアウトドアの楽しさを伝えたいという思いが根底にあります。
初心者に優しいブランドでありたいという創業の原点
「三流メーカー」という言葉は、決して自虐ではありません。大手ブランドや特定のサブカルチャーの枠に囚われることなく、常に挑戦者としての自由な精神を保ち続けたいという意志の表れなのです。
斎藤氏が目指す「一流」とは、企業の規模や売上ではなく、次のような本質的な部分での卓越性です。
震災をきっかけに「誰もが再び外で遊ぶきっかけを作りたい」という使命から生まれたパーゴワークス。ビギナーや若い人にやさしいブランドでありたいという願いは、単なる市場戦略ではなく、ブランドの根源的な使命から生まれた道徳的な要請なのです。エントリー層への扉を広く開けておくことこそ、「一流の三流メーカー」が目指す理想の姿といえるでしょう。
BUDDYやRUSH、NINJAに見るパーゴワークスのものづくりの真髄
パーゴワークスの哲学は、具体的な製品となって初めてユーザーの手元に届きます。代表的な3つのシリーズには、それぞれに開発秘話があり、ブランドの「丸いけど尖っている」という理念が見事に体現されています。ユーザーとの対話、遊び心、そして妥協なき開発姿勢を、製品開発の裏側から覗いてみましょう。
トレイルランナーと10年間キャッチボールして生まれたRUSHシリーズ
RUSHシリーズのルーツは、斎藤氏がブランド設立以前に遡ります。トレイルランニングレースの最高峰「ハセツネCUP」に出場する友人たちのために、カスタムパックを製作していたことが始まりでした。
当時市場を席巻していた海外製の複雑なレース用ベストは、初心者には敷居が高すぎたのです。RUSHシリーズの進化の過程には、次のような特徴があります。
パーゴワークスはトップ選手をスポンサードするのではなく、彼らと共に成長する道を選びました。この「Designed by the Runners」という姿勢こそが、RUSHシリーズを本物のトレランパックへと進化させたのです。
手裏剣型タープに「俺、天才?!」と思った瞬間
NINJAシリーズの象徴的な製品である手裏剣型のタープ。この独特な形状を思いついた時、斎藤氏は「俺、天才?!」と思ったそうです。ありきたりの四角形や六角形を退け、このユニークなデザインに辿り着いた瞬間は、まさに創造的な閃きだったといえるでしょう。
NINJAシリーズの革新的な特徴として、以下のようなものがあります。
「NINJA」という名前は、軽さとステルス性、そして忍者のような賢い道具使いを連想させます。遊び心と機能性を見事に両立させたこのシリーズは、日本の美意識とアウトドア自由主義の融合といえるでしょう。
100個以上のプロトタイプから生まれる妥協なき製品開発
パーゴワークスの開発プロセスは、まさに「圧倒的な数とスピード」という言葉に尽きます。RUSHシリーズの開発では、なんと150個以上ものプロトタイプを制作。実際のユーザー10名による長期フィールドテストを実施するなど、徹底的な実地検証を行っています。
この妥協なき開発姿勢は、次のようなプロセスに表れています。
テクニカルなバックパックの量産品を開発できるスタジオは、現在の日本にはほとんど存在しません。この希少な自社開発機能こそが、パーゴワークスの「圧倒的な強み」であり、イノベーションの源泉となっているのです。
【まとめ】パーゴワークス(PAAGOWORKS)が歩んできた歴史
2011年の東日本大震災から14年。「外に出ようぜ」というメッセージと共に誕生したパーゴワークスは、日本のアウトドア文化に確実な足跡を残してきました。創業者・斎藤徹氏の「自分が道具を作ることで、人を外に連れ出せるかもしれない」という想いは、今や多くの登山者の心に届いています。
これらすべてが融合したパーゴワークスの製品は、単なる道具を超えた存在となりました。
日本人の体型に最適化された技術力、ユーザーとの対話から生まれる革新的な製品、そして何より「人間らしく生きるために必要な時間」を提供するという哲学。
BUDDYやRUSH、NINJAシリーズに代表される製品群は、これからも日本の山を愛する人々と共に歩み続けるでしょう。震災という困難から生まれたこのブランドが、今日も誰かの背中を押し、新たな冒険へと導いているのです。